出版・販売季刊「音楽鑑賞教育」: 2024年度バックナンバー
Vol.60(2025年1月発行)
B5判 70ページ
全ページカラー
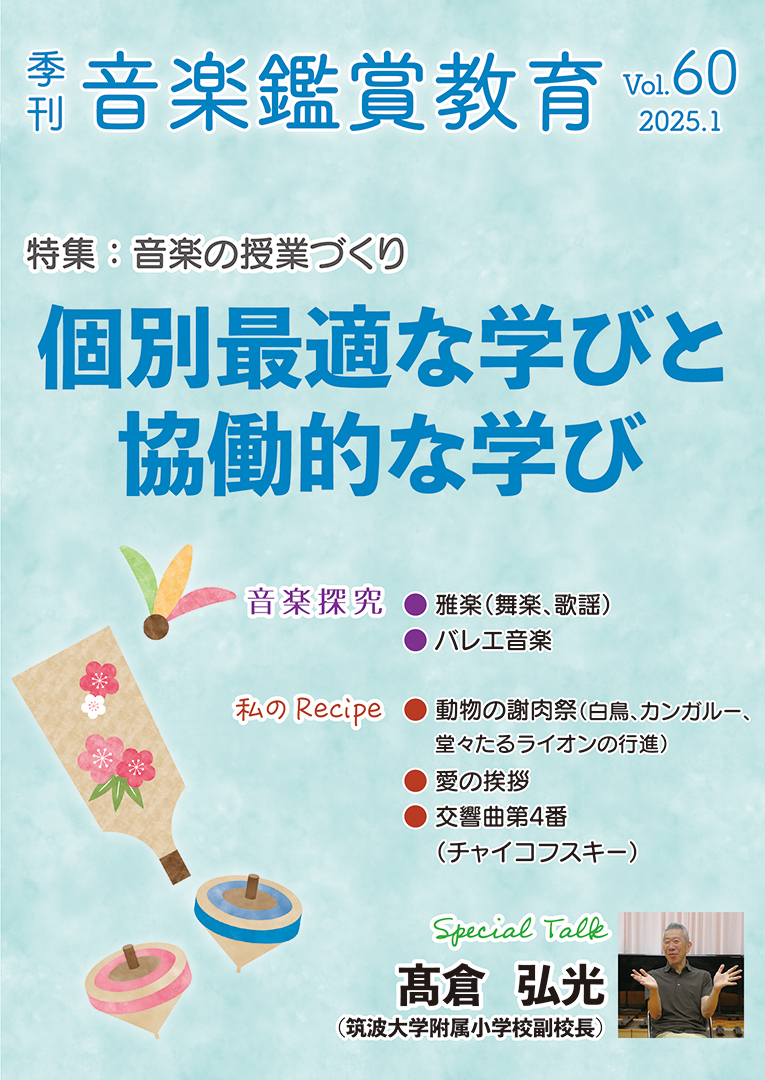
| 巻頭言 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 音楽の教師によって学校は変わる | 工藤豊太 (東京音楽大学特任教授) | |||
| SPECIAL TALK | ||||
| 子どもの“?”を大切にする授業を | ゲスト:髙倉弘光 (筑波大学附属小学校副校長) | |||
| 特集:個別最適な学びと協働的な学び | ||||
| テーマ設定の趣旨 | 「学びの時間と空間の多様化」がもたらす音楽学習の深化と拡大 | 山下薫子 (東京藝術大学教授/季刊「音楽鑑賞教育」編集委員) |
||
| 実践 | 「個別最適な学び」と「協働的な学び」との一体的な充実 | |||
| 小学校 | 方法ではなく目的を明確にした授業づくりを | 平野次郎 (筑波大学附属小学校教諭) | ||
| 「個別最適な学び」と「協働的な学び」につながる、ふり返りカード・題材構成(年間指導計画)の工夫 | 新田万里子 (島根県松江市立大庭小学校教諭) | |||
| 中学校 | 主体的・協働的な学びのための合唱練習用アプリ活用の可能性 | 中内悠介 (東京学芸大学附属世田谷中学校教諭) | ||
| 「自己選択」と「自己調整」を大切にした音楽科の授業づくり ~すべての生徒が音楽活動の楽しさを体験できる授業を目指して~ | 重黒木靜 (千葉県船橋市立葛飾中学校教諭) | |||
| 高等学校 | 音楽をシェアする喜び 「個別最適な学び」と「協働的な学び」の融合を目指して | 片野響子 (東京都立調布南高等学校音楽科主任教諭) | ||
| 論考 | 自律的な学び手を育成するための指導性の発揮 ――個別最適な学びと協働的な学びを視野に入れて―― | 田村 学 (文部科学省初等中等教育局主任視学官) | ||
| まとめ | 個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実をめざして | 本多佐保美 (千葉大学教授/季刊「音楽鑑賞教育」編集委員) |
||
| 音楽探究 | ||||
| 雅楽(舞楽、歌謡) | 寺内直子 (神⼾⼤学教授) | |||
| バレエ音楽 | 永井玉藻 (白百合女子大学非常勤講師) | |||
| 私のRecipe | ||||
| せんりつのとくちょうを感じ取ろう 教材曲:組曲《動物の謝肉祭》から『白鳥』『カンガルー』『堂々たるライオンの行進』(サン=サーンス) |
関 智子 (東京都東村山市立久米川東小学校主幹教諭) | |||
| 演奏表現の違いを感じ取りながら味わって鑑賞しよう 教材曲:『愛の挨拶』(エルガー) |
山下敦史 (北海道札幌市立中央中学校教頭) | |||
| 交響曲の魅力を探ろう ――「学習者主体の授業」への取組―― 教材曲:交響曲第4番(チャイコフスキー) |
新福一孝 (鹿児島県鹿児島市立武岡中学校教頭) | |||
| 特別寄稿 | ||||
| 今後の音楽科授業の改善に向けて | 志民一成 (文部科学省初等中等教育局視学官/文化庁参事官(芸術文化担当)付教科調査官/国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官) |
|||
| 美術の楽しみ | ||||
| 初富士 | 河野元昭 (東京大学名誉教授) | |||
| 私の音楽鑑賞指導論 | ||||
| よりよい鑑賞指導への試み | 江田 司 (元名古屋学院⼤学教授) | |||
| 本の紹介 | ||||
|
小山文加 (認定NPO法人カタリバ/国立音楽大学非常勤講師) | |||
| 市販DISCを教材に | ||||
| 私が工夫している授業紹介 | ||||
| 表現活動の実感を伴った学びから、味わって聴くことへ | 齋藤文惠 (千葉県千葉市立検見川小学校) | |||
| 全日音研のページ | ||||
| 令和6年度全日本音楽教育研究会全国大会旭川上川大会を終えて | 米津理臣 (旭川上川大会実行委員長/北海道美瑛町立美瑛東小学校長) |
|||
| ONKAN Information | ||||
| ONKANインターネットセミナー2024 第2回 | ||||
Vol.59(2024年10月発行)
B5判 70ページ
全ページカラー
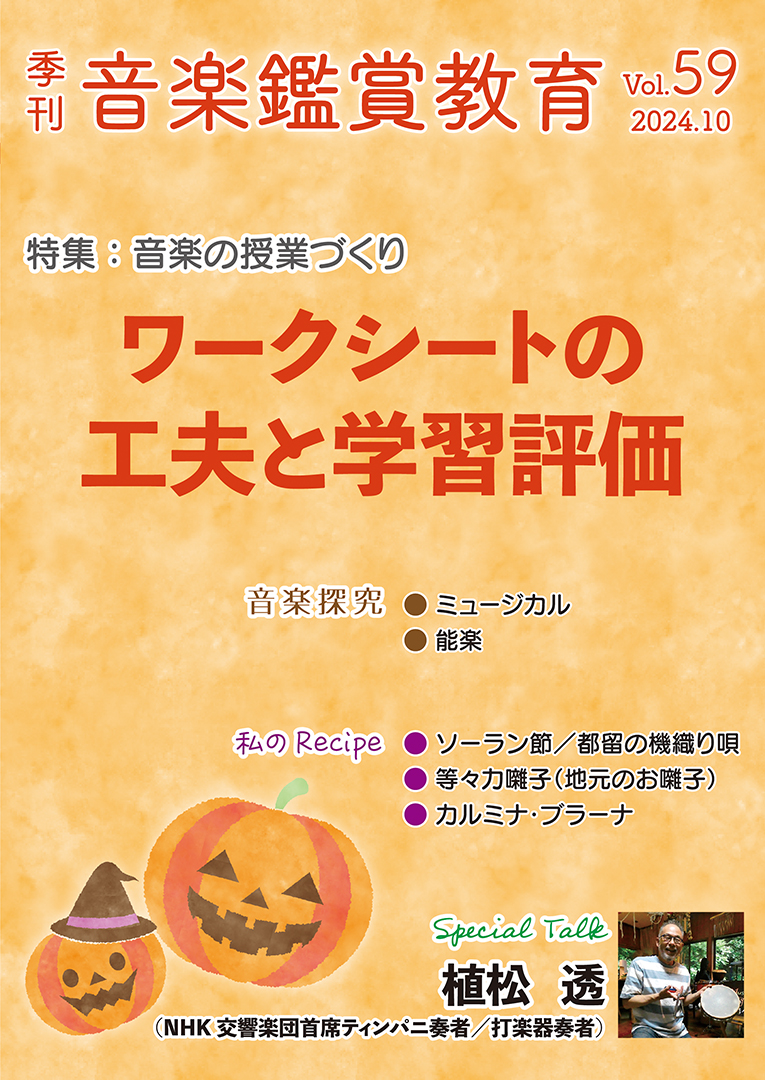
| 巻頭言 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 音楽の教科は人格形成の一隅を担うことができるのだろうか | 工藤豊太 (東京音楽大学特任教授) | |||
| SPECIAL TALK | ||||
| 正解のない打楽器だからできることがある | ゲスト:植松 透 (NHK交響楽団首席ティンパニ奏者/打楽器奏者) |
|||
| 特集:ワークシートの工夫と学習評価 | ||||
| テーマ設定の趣旨 | ワークシートの役割と評価とのつながり | 藤沢章彦 (元国立音楽大学教授/季刊「音楽鑑賞教育」編集委員) |
||
| 実践 | 子どもの学びを深めるワークシートの工夫 | |||
| 小学校 | ICTを活用したワークシートの工夫 | 鈴木沙矢佳 (東京都板橋区立中根橋小学校主任教諭) | ||
| 見通しをもった主体的な学びのために | 河合道子 (大阪府大阪市立東粉浜小学校教諭) | |||
| 中学校 | ワークシートの作成と授業での使い方 | 髙道有美子 (東京都世田谷区立芦花中学校主任教諭) | ||
| 生徒の可能性を引き出すワークシート | 島田靖子 (大阪府大阪市立瓜破西中学校主務教諭) | |||
| 高等学校 | 感じる心を引き出すワークシートを目指して | 西岡哲也 (佐賀県立小城高等学校教諭) | ||
| 論考 | ワークシートの内容と使い方は授業者が決める | 酒井美恵子 (国立音楽大学教授) | ||
| まとめ | ワークシートが授業のPDCAを推進する | 大熊信彦 (東邦音楽大学特任教授/季刊「音楽鑑賞教育」編集委員) |
||
| 音楽探究 | ||||
| ミュージカル | 辻佐保子 (静岡大学講師) | |||
| 能楽 | 三浦裕子 (武蔵野大学教授・能楽資料センター長) | |||
| 私のRecipe | ||||
| 郷土の音楽(民謡)に親しもう 教材曲:『ソーラン節』(北海道)/『都留の機織り唄』(山梨県都留市) |
和智宏樹 (山梨県上野原市立上野原小学校教諭) | |||
| 郷土の音楽を楽しもう! 「やってみる」ことから地元の「祭囃子」を鑑賞する 教材曲:『等々力囃子』(東京都世田谷区) |
清水宏美 (玉川大学教授) | |||
| オルフのカルミナ・ブラーナを楽しもう 3拍子の面白さを感じながら鑑賞する 教材曲:《カルミナ・ブラーナ》から(オルフ) |
岩本達明 (前神奈川県立湘南高等学校教諭) | |||
| 美術の楽しみ | ||||
| 菊 | 河野元昭 (東京大学名誉教授) | |||
| 私の音楽鑑賞指導論 | ||||
| 旋律を聴くということ | 山本幸正 (埼玉学園大学教授) | |||
| 音楽教育ノート | ||||
| ミュージッキングと私 | 西島千尋 (金沢大学人間社会研究域学校教育系) | |||
| 本の紹介 | ||||
|
市川 恵 (東京藝術大学准教授) | |||
| 市販DISCを教材に | ||||
| 私が工夫している授業紹介 | ||||
| 日本各地に伝わる民謡や郷土芸能に親しもう ~代用品を用いた「こきりこ」体験から地元の郷土芸能へ~ | 岸 明子 (埼玉県桶川市立日出谷小学校教諭) | |||
| 全日音研のページ | ||||
| 令和6年度全日音研第28期後期 本部各支部長の皆様をご紹介します | 菊本和仁 (全日本音楽教育研究会本部事務局長) | |||
| ONKAN Information | ||||
| ONKAN 授業づくりセミナー2024 | ||||
Vol.58(2024年7月発行)
B5判 70ページ
全ページカラー
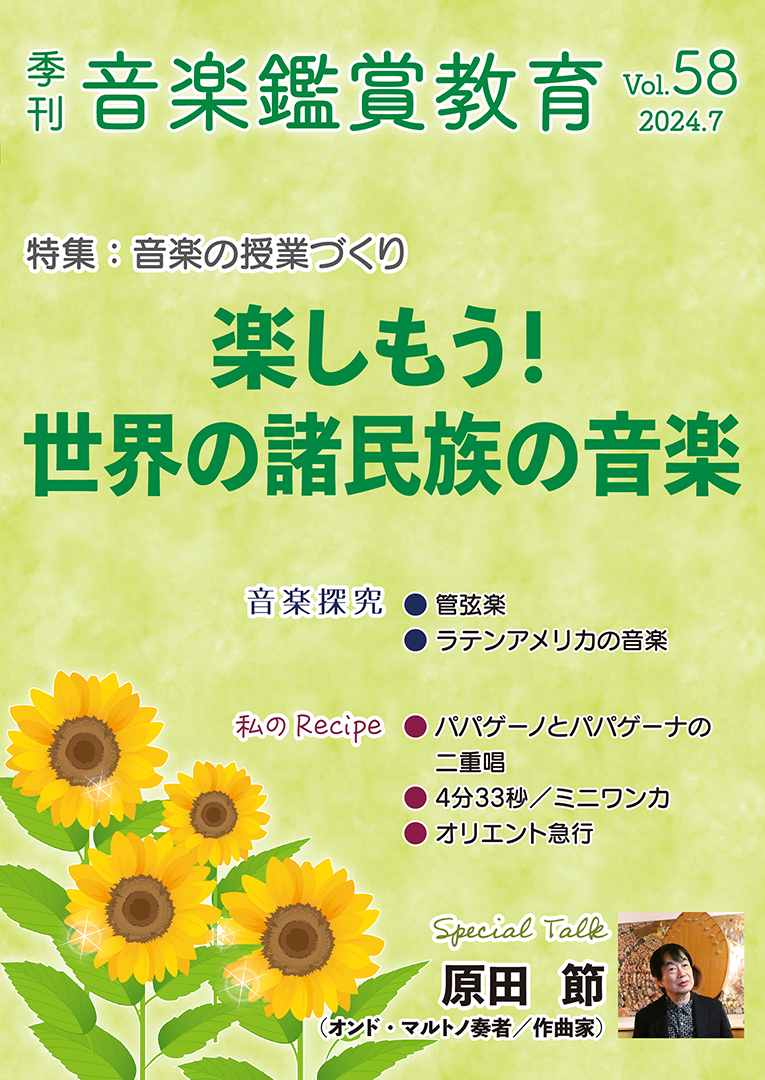
| 巻頭言 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 変化する教員採用試験で将来の音楽教員はどうなるだろう | 工藤豊太 (東京音楽大学特任教授) | |||
| SPECIAL TALK | ||||
| 音楽の先にあるものを表現したい | ゲスト:原田 節 (オンド・マルトノ奏者/作曲家) | |||
| 特集:楽しもう! 世界の諸民族の音楽 | ||||
| テーマ設定の趣旨 | 子どもたちの音楽の世界が一段と広がっていく実践を | 大熊信彦 (東邦音楽大学特任教授/季刊「音楽鑑賞教育」編集委員) |
||
| 実践 | 世界の諸民族の音楽の魅力や楽しさを体験 | |||
| 小学校 | 諸外国の音楽の様式の特徴や、そのよさの感受を促すための授業づくり | 松下行馬 (兵庫県神戸市立桜の宮小学校教諭) | ||
| アフリカのペンタトニックをもとに音楽をつくろう ~アフリカの音楽との出合い~ | 村上水絵 (埼玉県川口市立舟戸小学校教諭) | |||
| 中学校 | 音楽の旅に出よう! 新たな発見と知る喜び | 樋口紘子 (東京都世田谷区立喜多見中学校主任教諭) | ||
| 世界の声の音楽の魅力に探究的な学習を通して迫ろう | 馬場瑞絵 (福岡県福岡市立北崎中学校指導教諭) | |||
| 高等学校 | 表現領域と鑑賞領域からつなげる「世界の諸民族の音楽」の学び | 赤川敏子 (神奈川県立横須賀大津高等学校総括教諭) | ||
| 論考 | 世界の多様な音楽を、もっと身近に、もっと自分事として! | 桐原 礼 (信州大学准教授) | ||
| まとめ | みんなちがって、みんないい ――その先を見据えて―― | 山下薫子 (東京藝術大学教授/季刊「音楽鑑賞教育」編集委員) |
||
| 音楽探究 | ||||
| 管弦楽 楽器の多様さと発展 | 小岩信治 (一橋大学教授) | |||
| ラテンアメリカの音楽 | 石橋 純 (東京大学教授) | |||
| 私のRecipe | ||||
| 歌声の響きを感じとろう ~いろいろなリズムを感じとろう 教材曲:『歌のにじ』(佐田和夫作詞,岡部栄彦作曲)/歌劇《魔笛》から『パパゲーノとパパゲーナの二重唱』(モーツァルト)/『クラッピング・ファンタジー第7番(楽しいマーチ)』(長谷部匡俊) |
佐藤幸子 (埼玉県所沢市立林小学校教諭) | |||
| 声による音楽表現にチャレンジ! 音風景を声で描く創作を通して、“音”から“音楽”になる表現の可能性を探る 教材曲:『4分33秒』(ケージ)/『ミニワンカ』(マリー・シェイファー) |
北 典子 (福井大学連合教職大学院非常勤講師) | |||
| 「鑑賞マップ」を活用した新しい鑑賞方法の模索 教材曲:『オリエント急行』(スパーク) |
末石忠史 (洗足学園音楽大学教授) | |||
| 特別寄稿 | ||||
| 音楽科・芸術科音楽における「主体的に学習に取り組む態度」の指導と評価を考える | 河合紳和 (国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官/文化庁参事官(芸術文化担当)付教科調査官/文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官) |
|||
| 美術の楽しみ | ||||
| 雷 | 河野元昭 (東京大学名誉教授) | |||
| 私の音楽鑑賞指導論 | ||||
| 小さい音を聴くことから | 渡邊麗子 (元音楽授業研究の会顧問/NPO法人特別支援教育研究会未来教室講師) |
|||
| 本の紹介 | ||||
|
小山文加 (認定NPO法人カタリバ/国立音楽大学非常勤講師) |
|||
| 市販DISCを教材に | ||||
| 私が工夫している授業紹介 | ||||
| 比較鑑賞によって質的な違いを考え、音楽の魅力を感じ取る ~ロイロノートを活用した意見共有を通して~ | 萩生真愛 (愛知県立豊橋東高等学校) | |||
| 全日音研のページ | ||||
| 令和6年度全日音研全国大会旭川上川大会に向けて | 菊本和仁 (全日本音楽教育研究会本部事務局長) | |||
Vol.57(2024年4月発行)
B5判 74ページ
全ページカラー
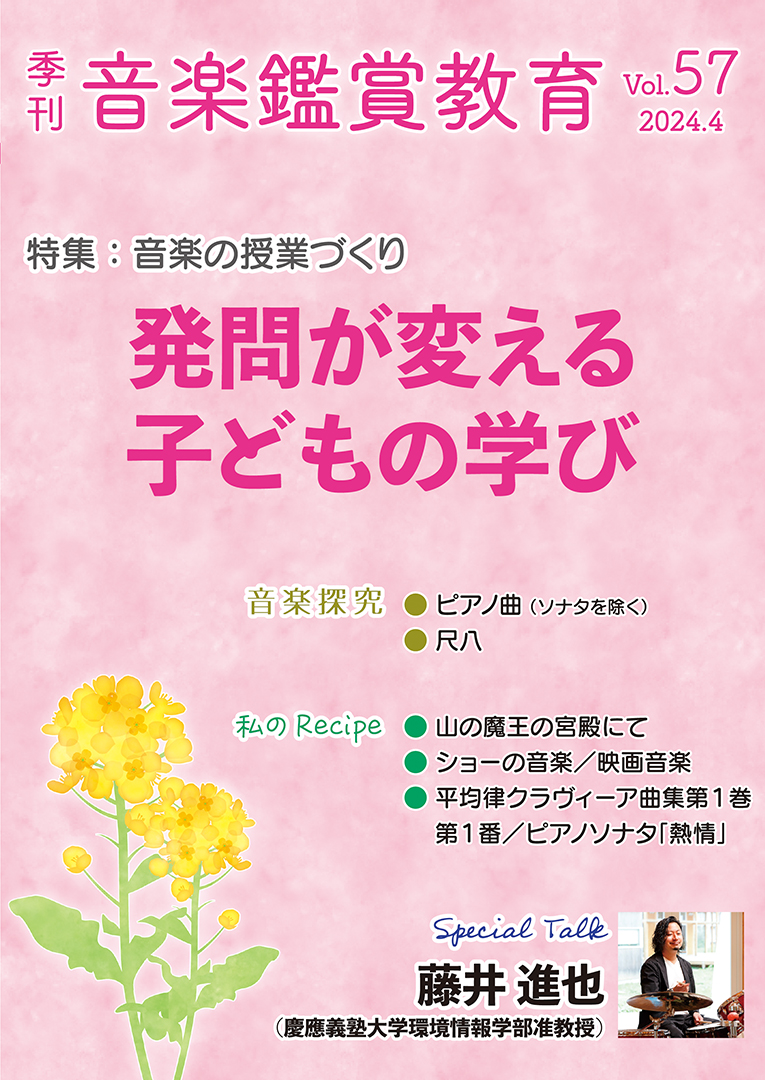
| 巻頭言 | ||||
|---|---|---|---|---|
| まずは音楽を聴こう、集中して聴くことで何かが見つかる | 工藤豊太 (東京音楽大学特任教授) | |||
| SPECIAL TALK | ||||
| 音楽を科学することはヒトのこころの理解につながる | ゲスト:藤井進也 (慶應義塾大学環境情報学部准教授) | |||
| 特集:発問が変える 子どもの学び | ||||
| テーマ設定の趣旨 | 主体的・協働的で深い学びにつながる発問を | 石上則子 (元東京学芸大学准教授・季刊「音楽鑑賞教育」編集委員) |
||
| 実践 | 発問を大切にした授業 | |||
| 小学校 | 子どもの思考が広がる発問を考える 〜鑑賞実践を通して〜 | 岩井智宏 (桐蔭学園小学部教諭) | ||
| 「学ぶ楽しさ」を引き出す発問と鑑賞授業のあり方 ~児童生徒が自分の言葉で表現する活動を通して~ | 磯 幸子 (茨城県水戸市立国田義務教育学校教諭) | |||
| 中学校 | 生きた授業を実現するために 〜社会における音楽の意味や役割について考えるまでの道のりを整える〜 | 野上華子 (京都教育大学附属桃山中学校教諭) | ||
| 主体的な学習を促す発問の工夫 | 中村麻里 (東京都中央区立銀座中学校教諭) | |||
| 高等学校 | 「なぜ?」という問いから深い学びにつなげる ~なぜ夜の女王のアリアは長調と短調が約半分ずつなのだろう?~ | 上原由美 (埼玉県立熊谷西高等学校教諭) | ||
| 論考 | 音楽科授業における「問い」を展望する | 高見仁志 (佛教大学教育学部教授) | ||
| まとめ | 子どもの学びを変える発問とは | 加藤富美子 (元東京音楽大学客員教授・季刊「音楽鑑賞教育」編集委員) |
||
| 音楽探究 | ||||
| ピアノ曲(ソナタを除く) | 福中冬子 (東京藝術大学教授) | |||
| 尺八 | 藤原道山 (尺八演奏家) | |||
| 私のRecipe | ||||
| 音楽が表している様子を思いうかべながら聴こう 教材曲:《ペール・ギュント》第1組曲から『山の魔王の宮殿にて』(グリーグ) |
半野田恵 (東京都立川市立第三小学校指導教諭) | |||
| ポピュラー音楽を楽しもう③ 楽曲がつくられた文化・歴史との関連を理解して鑑賞する 教材曲:『オースザンナ』『草競馬』『Old Joe』(フォスター)/『スワニー』(ガーシュイン)/『ムーンリバー』『ひまわり(愛のテーマ)』(ヘンリー・マンシーニ)/『いつか王子様が』(フランク・チャーチル) |
和田 崇 (東京音楽大学教授) | |||
| ピアノによる様々な表現効果を聴き取ろう 毎時間5~10分の隙間ユニットとしての鑑賞活動を取り入れた実践 教材曲:《平均律クラヴィーア曲集》第1巻から第1番『前奏曲とフーガ』(バッハ)/ピアノ・ソナタ第23番『熱情』(ベートーヴェン) |
白井友貴 (東京都立文京高等学校主任教諭) | |||
| 美術の楽しみ | ||||
| 蝶 | 河野元昭 (東京大学名誉教授) | |||
| 私の音楽鑑賞指導論 | ||||
| 子どもの感性を信じ音楽の魅力と正面から向き合う鑑賞授業を | 小松康裕 (全日本音楽教育研究会顧問) | |||
| 本の紹介 | ||||
|
市川 恵 (東京藝術大学准教授) | |||
| 市販DISCを教材に | ||||
| 私が工夫している授業紹介 | ||||
| 生徒が学びを実感できる授業の工夫 | 龍勝芳江 (福井県福井市足羽中学校) | |||
| 全日音研のページ | ||||
| 令和6年度全日本音楽教育研究会全国大会旭川上川大会(幼稚園部会大会、小・中学校部会大会、高等学校部会大会) 大会主題「音とつながる 心がつながる 学びがつながる」 |
米津理臣 (旭川上川大会運営委員長) | |||
| 音鑑の事業紹介 | ||||
|
||||
| 2023年度 音楽鑑賞教育振興 助成研究募集 入選研究計画論文 | ||||
| 音楽鑑賞における個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実の研究 ~自ら探究的に鑑賞する児童生徒の育成を目指して~ | ミュージック エデュケーション メッセ (研究グループ代表:山田聡(つくば市教育委員会)) |
|||