出版・販売季刊「音楽鑑賞教育」: 平成28年度バックナンバー
Vol.28(平成29年1月発行)
B5判 64ページ
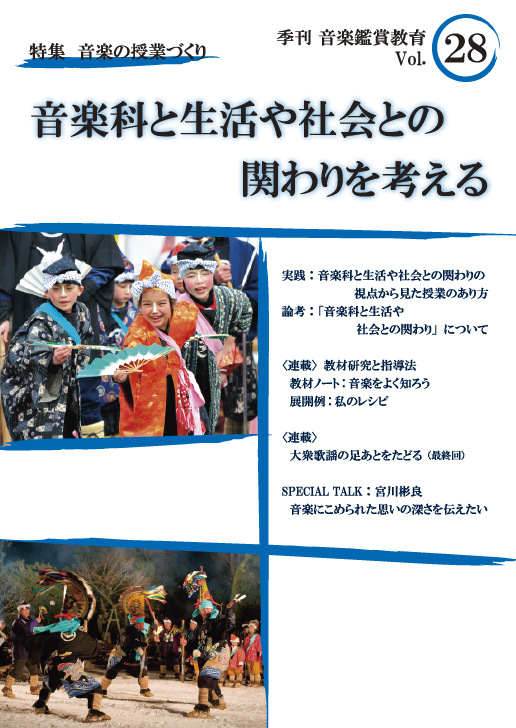
| 巻頭言 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 音楽鑑賞活動と「総合」の授業 | 辻村哲夫 (公益財団法人音楽鑑賞振興財団常務理事) | |||
| SPECIAL TALK | ||||
| 音楽にこめられた思いの深さを伝えたい | ゲスト:宮川彬良 (作曲家・舞台音楽家) | |||
| 特集:音楽科と生活や社会との関わりを考える | ||||
| テーマ設定の趣旨 | 音楽と生活や社会との関わりの考察から、音楽科の学習の拡充を探る | 加藤徹也 (武蔵野音楽大学教授・季刊「音楽鑑賞教育」編集委員) |
||
| 実践 | 生活や社会との関わりの視点から見た授業のあり方 | |||
| 小学校 | 子どもたちの生活や社会と音楽を結び付けるための音楽学習 | 金田美奈子 (東京都文京区立駕籠町小学校指導教諭) | ||
| 地域の伝統や音楽を尊重し、その持続発展に貢献しようとする態度を育てる | 富樫真紀 (広島県東広島市立西条小学校教諭) | |||
| 中学校 | 音楽科の存在意義を示すために、生活や社会とつながる授業を | 原口 直 (東京学芸大学附属世田谷中学校教諭) | ||
| 特別支援 | 生活のなかに、自分で音楽を取り入れて楽しむ | 大宮幸子 (山形大学附属特別支援学校高等部教諭) | ||
| 高等学校 | 音や音楽が身の回りに溢れている生活との関わりのなかで | 國弘雅也 (埼玉県立川越高等学校教諭) | ||
| 論考 | 「音楽科と生活や社会との関わり」について | 秋元みさ子 (玉川大学非常勤講師) | ||
| まとめ | 児童生徒の1人ひとりが「音楽文化の担い手」としての意識や使命感をもつために | 山下薫子 (東京藝術大学教授・季刊「音楽鑑賞教育」編集委員) |
||
| 教材研究と指導法 | ||||
| 白鳥(組曲《動物の謝肉祭》より) | 教材ノート | 福中冬子 (東京藝術大学准教授) | ||
| 展開例 | 江田 司 (名古屋学院大学准教授) | |||
| 剣の舞(《ガイーヌ》より) | 教材ノート | 福中冬子 (東京藝術大学准教授) | ||
| 展開例 | 高倉弘光 (筑波大学附属小学校教諭) | |||
| ラプソディ・イン・ブルー | 教材ノート | 福中冬子 (東京藝術大学准教授) | ||
| 展開例 | 和田 崇 (東京音楽大学講師) | |||
| 雅楽「越天楽」 | 教材ノート | 遠藤 徹 (東京学芸大学教授) | ||
| 展開例 | 福井昭史 (長崎大学名誉教授) | |||
| 特別寄稿 | ||||
| 音楽科における授業改善の現状と課題IV ―小学校学習指導要領実施状況調査(音楽)の結果を中心に― |
津田正之 (国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官・文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官) |
|||
| 近代日本の大衆歌謡史〈最終回〉 | ||||
| 大衆歌謡の足あとをたどる …大衆音楽と音楽教育との相克 | 輪島裕介 (大阪大学大学院文学研究科准教授) | |||
| 本の紹介 | ||||
|
佐野 靖 (東京藝術大学教授) | |||
| 市販DISCを教材に | ||||
| 全日音研のページ | ||||
| 平成28年度全国大会 盛会裏に閉幕 | 小松康裕 (全日本音楽教育研究会本部事務局長) | |||
Vol.27(平成28年10月発行)
B5判 64ページ
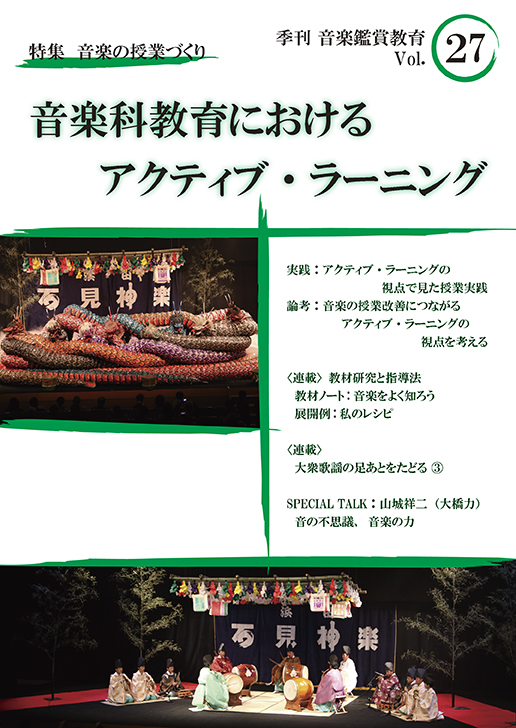
| 巻頭言 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 楽器の不思議を探る | 辻村哲夫 (公益財団法人音楽鑑賞振興財団常務理事) |
|||
| SPECIAL TALK | ||||
| 音の不思議、音楽の力 ―ハイパーハイレゾリューション音源の可能性― |
ゲスト:山城祥二(大橋 力) (芸能山城組組頭・生命科学者) |
|||
| 特集:音楽科教育におけるアクティブ・ラーニング | ||||
| テーマ設定の趣旨 | アクティブ・ラーニングで育つ子どもの姿 | 川池 聰 (公益財団法人音楽鑑賞振興財団理事・季刊「音楽鑑賞教育」編集委員) |
||
| 実践 | アクティブ・ラーニングの視点で見た授業実践 | |||
| 小学校 | 聴いて、感じて、考えて 音楽の面白さを発見! | 橋本絵理 (静岡県静岡市立葵小学校教諭) | ||
| 「省察」をともなう主体的な鑑賞の授業 ~「もう1回!」と声がかかる活動~ |
佐々木香織 (茨城県つくば市立春日学園義務教育学校教諭) |
|||
| 中学校 | 課題提示と学び合いの工夫から ―より深く、より関わりあって― |
水谷 愛 (埼玉県川越市立大東西中学校教諭) | ||
| 自ら感じ、仲間と深める鑑賞授業 | 上谷 舞 (広島県広島市立白木中学校教諭) | |||
| 高等学校 | 「学びに向かう力」を育む ~“学習プロセス”と“主体的な学びの過程の視覚化”に焦点を当てて~ |
坂本 将 (群馬県立長野原高等学校教諭) | ||
| 論考 | 音楽の授業改善につながるアクティブ・ラーニングの視点を考える | 権藤敦子 (広島大学教授) | ||
| まとめ | 音楽の授業における「主体的・対話的で深い学び」とは | 加藤富美子 (東京音楽大学教授・季刊「音楽鑑賞教育」編集委員) |
||
| 教材研究と指導法 | ||||
| パパゲーノとパパゲーナの二重唱 (パ・パ・パ)(歌劇《魔笛》より) |
教材ノート | 福中冬子 (東京藝術大学准教授) | ||
| 展開例 | 江田 司 (名古屋学院大学准教授) | |||
| 春の海 | 教材ノート | 千葉優子 (宮城道雄記念館資料室室長) | ||
| 展開例 | 高倉弘光 (筑波大学附属小学校教諭) | |||
| ガムラン | 教材ノート | 川口明子 (岩手大学教育学部教授) | ||
| 展開例 | 和田 崇 (東京音楽大学講師) | |||
| ボレロ | 教材ノート | 福中冬子 (東京藝術大学准教授) | ||
| 展開例 | 福井昭史 (長崎大学名誉教授) | |||
| 近代日本の大衆歌謡史 | ||||
| 大衆歌謡の足あとをたどる …昭和初期メディア産業の台頭 | 輪島裕介 (大阪大学大学院文学研究科准教授) | |||
| 本の紹介 | ||||
|
佐野 靖 (東京藝術大学教授) | |||
| 市販DISCを教材に | ||||
| 全日音研のページ | ||||
|
小松康裕 (全日本音楽教育研究会本部事務局長) | |||
| 音鑑の事業紹介 | ||||
|
||||
Vol.26(平成28年7月発行)
B5判 64ページ
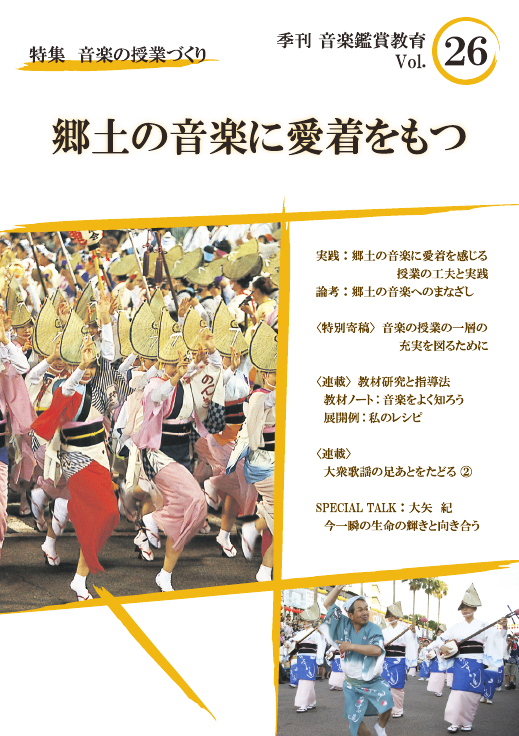
| 巻頭言 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラ・マルセイエーズ | 辻村哲夫 (公益財団法人音楽鑑賞振興財団常務理事) |
|||
| SPECIAL TALK | ||||
| 今一瞬の生命(いのち)の輝きと向き合う | ゲスト:大矢 紀 (日本画家) | |||
| 特集:郷土の音楽に愛着をもつ | ||||
| テーマ設定の趣旨 | 楽しく聴いて、体験する郷土の音楽 | 藤沢章彦 (文教大学講師・季刊「音楽鑑賞教育」編集委員) |
||
| 実践 | 郷土の音楽に愛着を感じる授業の工夫と実践 | |||
| 小学校 | 郷土の音楽を知ることで誇りをもって自分を表現できるように ~目黒ばやしの鑑賞を通して~ |
柁原 年 (東京都目黒区立鷹番小学校非常勤教員) | ||
| 音楽の背景を疑似体験して、唄を自分のものに! | 永井民子 (新潟県小千谷市立片貝小学校教諭) | |||
| 中学校 | 今に伝わる民謡の魅力を生かして ~北海道の民謡や芸能を教材に~ |
萬 司 (北海道札幌市立澄川中学校主幹教諭) | ||
| 「つながる」をキーワードにした「郷土の音楽」の授業 | 仲地綾子 (沖縄県うるま市立具志川中学校教諭) | |||
| 高等学校 | 「郷土の音楽」にこそ隠れた魅力がつまっている!! | 上岡和代 (宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校教諭) | ||
| 論考 | 郷土の音楽へのまなざし | 伊野義博 (新潟大学教授) | ||
| まとめ | 人への思いをはせることから | 佐野享子 (季刊「音楽鑑賞教育」編集委員) | ||
| 教材研究と指導法 | ||||
| 行進曲(《くるみ割り人形》より) | 教材ノート | 福中冬子 (東京藝術大学准教授) | ||
| 展開例 | 江田 司 (名古屋学院大学准教授) | |||
| ファランドール | 教材ノート | 福中冬子 (東京藝術大学准教授) | ||
| 展開例 | 高倉弘光 (筑波大学附属小学校教諭) | |||
| アランフェス協奏曲 | 教材ノート | 福中冬子 (東京藝術大学准教授) | ||
| 展開例 | 和田 崇 (東京音楽大学講師) | |||
| 能「羽衣」 | 教材ノート | 森田都紀 (京都造形芸術大学准教授) | ||
| 展開例 | 福井昭史 (長崎大学名誉教授) | |||
| 特別寄稿 | ||||
| 音楽の授業の一層の充実を図るために ―今後の動向を見据えて― |
臼井 学 (国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官・文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官) |
|||
| 近代日本の大衆歌謡史 | ||||
| 大衆歌謡の足あとをたどる …大正期の芸術活動 | 輪島裕介 (大阪大学大学院文学研究科准教授) | |||
| 本の紹介 | ||||
|
佐野 靖 (東京藝術大学教授) | |||
| 市販DISCを教材に | ||||
| 全日音研のページ | ||||
| 地域間・校種間の授業を繋ぐ研究大会 | 小松康裕 (全日本音楽教育研究会本部事務局長) | |||
Vol.25(平成28年4月発行)
B5判 64ページ
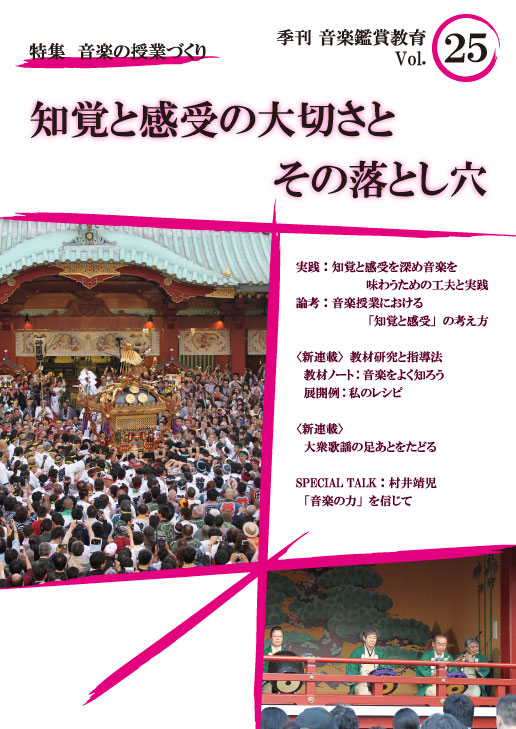
| 巻頭言 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 子どもたちを音楽劇場に連れて行こう | 辻村哲夫 (公益財団法人音楽鑑賞振興財団常務理事) |
|||
| SPECIAL TALK | ||||
| 「音楽の力」を信じて | ゲスト:村井靖児 (聖徳大学教授・日本音楽療法学会副理事長) |
|||
| 特集:知覚と感受の大切さとその落とし穴 | ||||
| テーマ設定の趣旨 | 知覚と感受の先にあるものを見据えて | 山下薫子 (東京藝術大学教授・季刊「音楽鑑賞教育」編集委員) |
||
| 実践 | 知覚と感受を深め音楽を味わうための工夫と実践 | |||
| 小学校 | 「聴いて・感じて」を大切に…… | 藤本章子 (東京都台東区立上野小学校教諭) | ||
| 1つの要素から広がる知覚・感受 | 林 千穂 (静岡県静岡市立城北小学校教諭) | |||
| 中学校 | 交流し、高め合う音楽活動をめざして ~音楽のある心豊かな人生を~ |
菅原吏枝子 (宮城県気仙沼市立鹿折中学校教諭) | ||
| 知覚・感受は心との対話 ~鑑賞指導で培うメタ認知力~ |
森長はるみ (奈良県奈良市富雄第三小中学校教諭) | |||
| 高等学校 | 感受から知覚へ ~歌舞伎の実践を交えた鑑賞の授業~ |
水井 奏 (宮城県石巻好文館高等学校教諭) | ||
| 論考 | 音楽授業における「知覚と感受」の考え方 | 阪井 恵 (明星大学教授) | ||
| まとめ | 授業のさらなる充実・向上を目指して | 加藤徹也 (季刊「音楽鑑賞教育」編集委員) | ||
| 〈新連載〉教材研究と指導法 | ||||
| シンコペーテッド・クロック | 教材ノート | 福中冬子 (東京藝術大学准教授) | ||
| 展開例 | 江田 司 (名古屋学院大学准教授) | |||
| ハンガリー舞曲第5番 | 教材ノート | 福中冬子 (東京藝術大学准教授) | ||
| 展開例 | 高倉弘光 (筑波大学附属小学校教諭) | |||
| 展覧会の絵 | 教材ノート | 福中冬子 (東京藝術大学准教授) | ||
| 展開例 | 和田 崇 (元東京都江戸川区立瑞江第二中学校主幹教諭) | |||
| フーガ ト短調 | 教材ノート | 福中冬子 (東京藝術大学准教授) | ||
| 展開例 | 福井昭史 (元長崎大学教授) | |||
| 〈新連載〉近代日本の大衆歌謡史 | ||||
| 大衆歌謡の足あとをたどる …「演歌」について | 輪島裕介 (大阪大学大学院文学研究科准教授) | |||
| 本の紹介 | ||||
|
佐野 靖 (東京藝術大学教授) | |||
| 市販DISCを教材に | ||||
| 全日音研のページ | ||||
| ひびきあい つながり・ひろがる 音楽のメッセージ 〈平成28年度全日音研全国大会 函館・道南大会のご案内〉 |
金谷美也子 (函館・道南大会準備委員長) | |||
| 音鑑の事業紹介 | ||||
| 「音鑑・冬の勉強会2015」レポート | ||||