出版・販売季刊「音楽鑑賞教育」: 平成29年度バックナンバー
Vol.32(平成30年1月発行)
B5判 64ページ
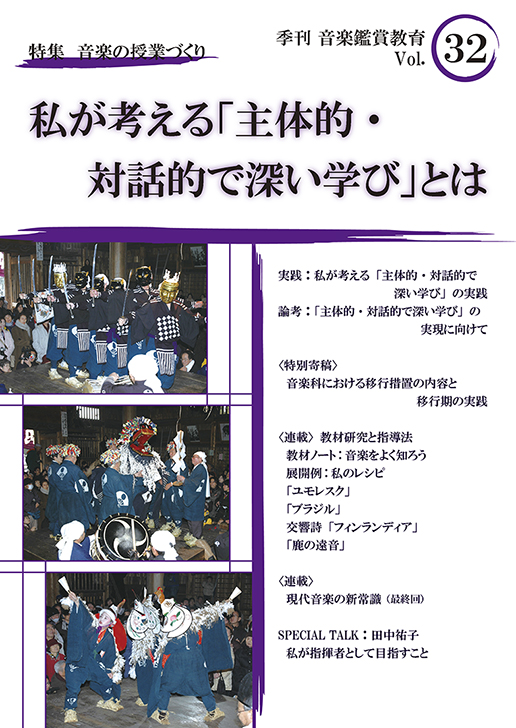
| 巻頭言 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2050年の音楽鑑賞は? | 丸山忠璋 (元武蔵野音楽大学教授) | |||
| SPECIAL TALK | ||||
| 私が指揮者として目指すこと ――人間の豊かさについて考える―― |
ゲスト:田中祐子 (指揮者) | |||
| 特集:私が考える「主体的・対話的で深い学び」とは | ||||
| テーマ設定の趣旨 | 新たな視点で実践を振り返り授業改善へ | 佐野享子 (横浜高等教育専門学校講師・季刊「音楽鑑賞教育」編集委員) |
||
| 実践 | 私が考える「主体的・対話的で深い学び」の実践 | |||
| 小学校 | 町田直樹 (お茶の水女子大学附属小学校教諭) | |||
| 黒田正子 (栃木県宇都宮市立簗瀬小学校教諭) | ||||
| 長谷川有里 (千葉県船橋市立八木が谷北小学校教頭) | ||||
| 村山香織 (新潟県新潟市立小須戸小学校教諭) | ||||
| 中学校 | 中村麻里 (東京都江戸川区立春江中学校教諭) | |||
| 千代島なつき (千葉県八街市立八街中学校教諭) | ||||
| 小川大輔 (広島県三原市立第一中学校教諭) | ||||
| 金本志秀 (宮崎大学教育学部附属中学校指導教諭) | ||||
| 高等学校 | 中内悠介 (東京都立深沢高等学校教諭) | |||
| 竹内 浩 (福井県立丹生高等学校教諭) | ||||
| 論考 | 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて ~流行で終わらせないために~ |
山下薫子 (東京藝術大学教授) | ||
| まとめ | 工夫と試行への挑戦を | 藤沢章彦 (季刊「音楽鑑賞教育」編集委員) | ||
| 教材研究と指導法 | ||||
| ユモレスク | 教材ノート | 奥田佳道 (音楽評論家) | ||
| 展開例 | 高倉弘光 (筑波大学附属小学校教諭) | |||
| ブラジル | 教材ノート | 渡辺 亮 (パーカッショニスト) | ||
| 展開例 | 江田 司 (名古屋学院大学准教授) | |||
| 交響詩「フィンランディア」 | 教材ノート | 福中冬子 (東京藝術大学教授) | ||
| 展開例 | 萬 司 (拓殖大学北海道短期大学教授) | |||
| 鹿の遠音 | 教材ノート | 福井昭史 (長崎大学名誉教授) | ||
| 展開例 | 和田 崇 (東京音楽大学講師) |
|||
| 特別寄稿 | ||||
| 音楽科における移行措置の内容と移行期の実践 | 津田正之 (国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官・文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官) |
|||
| 〈連載〉現代音楽の新常識〈最終回〉 | ||||
| 日本の「現代音楽」 ――新たな創造への歩み | 白石美雪 (武蔵野美術大学教授・音楽評論家) | |||
| 本の紹介 | ||||
|
佐野 靖 (東京藝術大学教授) | |||
| 市販DISCを教材に | ||||
| 全日音研のページ | ||||
| “ちむぐくる”に満ちた29年度全国大会沖縄大会(総合大会) 沖縄大会大学部会研究発表から「日韓音楽教育セミナー」の紹介 |
小松康裕 (全日本音楽教育研究会本部事務局長) | |||
| 音鑑の事業紹介 | ||||
| 音鑑・ICT勉強会2017 | ||||
Vol.31(平成29年10月発行)
B5判 64ページ
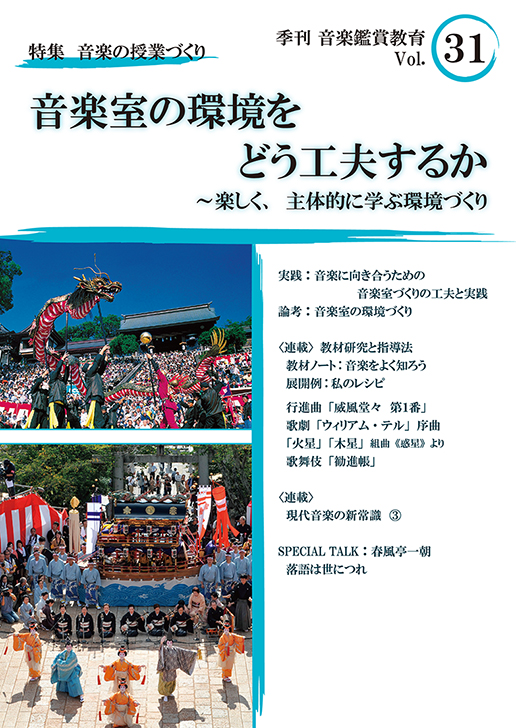
| 巻頭言 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 音楽と連想 | 丸山忠璋 (元武蔵野音楽大学教授) | |||
| SPECIAL TALK | ||||
| 「落語」は世につれ ――語りで演出する豊穣な物語の世界―― |
ゲスト:春風亭一朝 (落語家) | |||
| 特集:音楽室の環境をどう工夫するか | ||||
| テーマ設定の趣旨 | 子どもたちが、楽しく学べる音楽室 | 川池 聰 (季刊「音楽鑑賞教育」編集委員) | ||
| 実践 | 音楽に向き合うための音楽室づくりの工夫と実践 | |||
| 小学校 | 音楽室環境の工夫 ~集中して学ぶ環境づくり~ |
毛木大介 (東京都江東区立東雲小学校主任教諭) | ||
| 子どもたちの力で伸びてゆく音楽室 | 黒沼駿一 (横浜国立大学教育学部附属鎌倉小学校教諭) | |||
| 中学校 | 「主体的・対話的で深い学び」を実現する音楽室づくり | 小作典子 (東京都杉並区立荻窪中学校指導教諭) | ||
| 行きたい音楽室、いつまでもいたい音楽室づくりをめざして | 長者久保希史子 (青森県八戸市立中沢中学校教頭) | |||
| 高等学校 | 音に対して主体的! ~音楽室はコンサートホール~ |
伴野和章 (群馬県立太田東高等学校教諭) | ||
| 論考 | 音楽室の環境づくり ~学校における特別な空間を~ |
齊藤忠彦 (信州大学教育学部教授) | ||
| まとめ | 環境づくりの工夫が授業を変える | 佐野享子 (季刊「音楽鑑賞教育」編集委員) | ||
| 教材研究と指導法 | ||||
| 行進曲「威風堂々 第1番」 | 教材ノート | 福中冬子 (東京藝術大学教授) | ||
| 展開例 | 高倉弘光 (筑波大学附属小学校教諭) | |||
| 歌劇「ウィリアム・テル」序曲 | 教材ノート | 奥田佳道 (音楽評論家) | ||
| 展開例 | 江田 司 (名古屋学院大学准教授) | |||
| 火星/木星 (組曲《惑星》より) | 教材ノート | 福井昭史 (長崎大学名誉教授) | ||
| 展開例 | 和田 崇 (東京音楽大学講師) | |||
| 歌舞伎「勧進帳」 | 教材ノート | 配川美加 (東京藝術大学非常勤講師) | ||
| 展開例 | 萬 司 (拓殖大学北海道短期大学教授) |
|||
| 〈連載〉現代音楽の新常識 | ||||
| ジョン・ケージの時代 ――モダニズムからポストモダニズムへ | 白石美雪 (武蔵野美術大学教授・音楽評論家) | |||
| 本の紹介 | ||||
|
佐野 靖 (東京藝術大学教授) | |||
| 市販DISCを教材に | ||||
| 音鑑の事業紹介 | ||||
| 音鑑・夏の勉強会2017「よりより授業を求めて」 | ||||
| 全日音研のページ | ||||
| 平成29年度の全日音研各支部長の皆様をご紹介します | 小松康裕 (全日本音楽教育研究会本部事務局長) | |||
Vol.30(平成29年7月発行)
B5判 64ページ
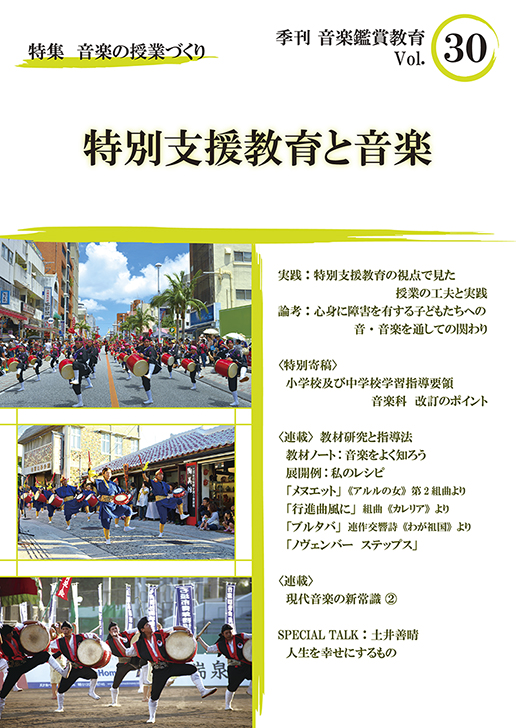
| 巻頭言 | ||||
|---|---|---|---|---|
| “聞く”と“聴く” | 丸山忠璋 (元武蔵野音楽大学教授) | |||
| SPECIAL TALK | ||||
| 人生を幸せにするもの ――食べることがくらしの中心―― |
ゲスト:土井善晴 (料理研究家) | |||
| 特集:特別支援教育と音楽 | ||||
| テーマ設定の趣旨 | 見つける・伸ばす・生かす | 加藤富美子 (東京音楽大学教授・季刊「音楽鑑賞教育」編集委員) |
||
| 実践 | 特別支援教育の視点で見た授業の工夫と実践 | |||
| 特別支援学校 小学校 |
1人ひとりの音楽の受けとめ方を考慮した楽器を用いた活動 | 遠藤芙美 (静岡県立御殿場特別支援学校小学部教諭) | ||
| 特別支援学校 中学校 |
みんなちがって、みんないい ~18人の個性がともに奏でる音楽表現~ |
工藤傑史 (筑波大学附属大塚特別支援学校教諭) | ||
| 小学校 | 友だちと一緒に音楽を楽しもう | 村松東子 (東京都中野区立江原小学校教諭) | ||
| 高等学校 | 特別でなく、誰もが分かる、役に立つことを主眼においた授業 | 斉藤慎之介 (東京都立足立東高等学校教諭) | ||
| 音楽教室 | 自分らしく音楽を楽しむために ~音楽教室の活動のなかで~ |
森本みち子 (フロイデン音楽教室共同主宰) | ||
| 論考 | 心身に障害を有する子どもたちへの音・音楽を通しての関わり ~基本的な心構えに焦点を当てて~ |
遠山文吉 (元国立音楽大学教授・元東京藝術大学招聘教授) | ||
| まとめ | 音楽の特性を生かし、子どもたちのよさを伸ばす活動を目指して | 加藤徹也 (武蔵野音楽大学教授・季刊「音楽鑑賞教育」編集委員) |
||
| 教材研究と指導法 | ||||
| メヌエット (《アルルの女》第2組曲より) | 教材ノート | 福中冬子 (東京藝術大学教授) | ||
| 展開例 | 高倉弘光 (筑波大学附属小学校教諭) | |||
| 行進曲風に (《カレリア》組曲より) | 教材ノート | 福井昭史 (長崎大学名誉教授) | ||
| 展開例 | 江田 司 (名古屋学院大学准教授) | |||
| ブルタバ (連作交響詩《わが祖国》より) | 教材ノート | 奥田佳道 (音楽評論家) | ||
| 展開例 | 和田 崇 (東京音楽大学講師) | |||
| ノヴェンバー ステップス | 教材ノート | 福中冬子 (東京藝術大学教授) | ||
| 展開例 | 萬 司 (拓殖大学北海道短期大学教授) |
|||
| 特別寄稿 | ||||
| 小学校及び中学校学習指導要領 音楽科 改訂のポイント | 臼井 学 (国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官・(併任)文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官) |
|||
| 〈連載〉現代音楽の新常識 | ||||
| 未知の音楽を求めて ――19世紀から20世紀へ | 白石美雪 (武蔵野美術大学教授・音楽評論家) | |||
| 本の紹介 | ||||
|
佐野 靖 (東京藝術大学教授) | |||
| 市販DISCを教材に | ||||
| 全日音研のページ | ||||
| 今後の全国大会開催ご紹介 ~ご参加お願い致します~ | 小松康裕 (全日本音楽教育研究会本部事務局長) | |||
| 音鑑の事業紹介 | ||||
| ONKAN Concert シリーズ“これが聴きたかった!” 第1回 ドイツリートで歌う 義太夫で語る 「魔王」 | ||||
Vol.29(平成29年4月発行)
B5判 72ページ
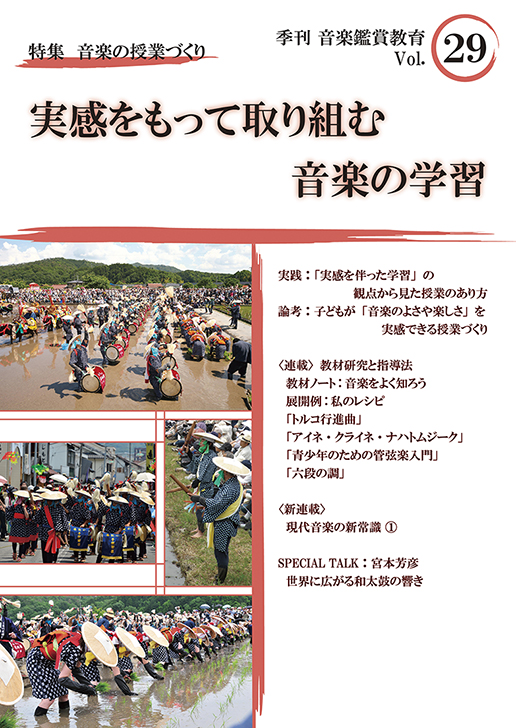
| 巻頭言 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 隻手の音声を聴け | 丸山忠璋 (元武蔵野音楽大学教授) | |||
| SPECIAL TALK | ||||
| 世界に広がる和太鼓の響き | ゲスト:宮本芳彦 (株式会社宮本卯之助商店社長) | |||
| 特集:実感をもって取り組む音楽の学習 | ||||
| テーマ設定の趣旨 | 体の快感、脳の快感、心の快感 | 藤沢章彦 (東京女子体育短期大学講師・季刊「音楽鑑賞教育」編集委員) |
||
| 実践 | 「実感を伴った学習」の観点から見た授業のあり方 | |||
| 小学校 | 楽しい音階指導が表現・鑑賞の深い学びにつながる | 宇佐美あかね (神奈川県横須賀市立大塚台小学校専科非常勤講師) |
||
| 「音楽の学び」を実感できる授業へ | 深澤啓太郎 (山梨県甲府市立北新小学校教諭) | |||
| 中学校 | 音楽の感じ方を豊かにする鑑賞指導 ――学習を通して広がった聴き方で楽曲の魅力を味わう姿をめざして |
祢津佐智恵 (長野県松本市立丸ノ内中学校教諭) | ||
| 仲間とともに音楽の深さを発見していく喜び ~効果的な発問で聴くポイントを導く~ |
白井友貴 (東京都品川区立東海中学校教諭) | |||
| 高等学校 | 音楽の喜びを味わえる、実感できる授業を | 古澤成樹 (東京都立南葛飾高等学校主幹教諭) | ||
| 論考 | 子どもが「音楽のよさや楽しさ」を実感できる授業づくり | 大熊信彦 (群馬県総合教育センター副所長) | ||
| まとめ | すべては、「できた」「わかった」と子どもが実感するところから始まる | 川池 聰 (季刊「音楽鑑賞教育」編集委員) | ||
| 教材研究と指導法 | ||||
| トルコ行進曲(ベートーヴェン) | 教材ノート | 福中冬子 (東京藝術大学准教授) | ||
| 展開例 | 高倉弘光 (筑波大学附属小学校教諭) | |||
| アイネ・クライネ・ナハトムジーク | 教材ノート | 福中冬子 (東京藝術大学准教授) | ||
| 展開例 | 江田 司 (名古屋学院大学准教授) | |||
| 青少年のための管弦楽入門 | 教材ノート | 奥田佳道 (音楽評論家) | ||
| 展開例 | 福井昭史 (長崎大学名誉教授) | |||
| 六段の調 | 教材ノート | 千葉優子 (宮城道雄記念館資料室室長) | ||
| 展開例 | 和田 崇 (東京音楽大学講師) |
|||
| 〈新連載〉現代音楽の新常識 | ||||
| 音楽の常識を超えて ――新たな地平を切り開いた芸術思潮 | 白石美雪 (武蔵野美術大学教授・音楽評論家) | |||
| 本の紹介 | ||||
|
佐野 靖 (東京藝術大学教授) | |||
| 市販DISCを教材に | ||||
| 全日音研のページ | ||||
| つなげよう未来へ 伝え合おう 音楽・ちむぐくる 〈平成29年度全日音研全国大会沖縄大会(総合大会)のご紹介〉 |
安次富功 (全日音研全国大会沖縄大会会長) | |||
| 平成28年度 第49回 音楽鑑賞教育振興 論文・作文募集 研究助成の部 入選研究計画論文 | ||||
| 音楽鑑賞を深めるための「小さな問い」と「本質に迫る問い」の研究 | 群馬県 音楽鑑賞を深める実践研究会 (代表:島田 聡 (群馬県立館林女子高等学校)) |
|||
| 音鑑の事業紹介 | ||||
| 音鑑・冬の勉強会2016「よりよい授業を求めて」リポート | ||||