出版・販売季刊「音楽鑑賞教育」: 2018年度バックナンバー
Vol.36(2019年1月発行)
B5判 64ページ
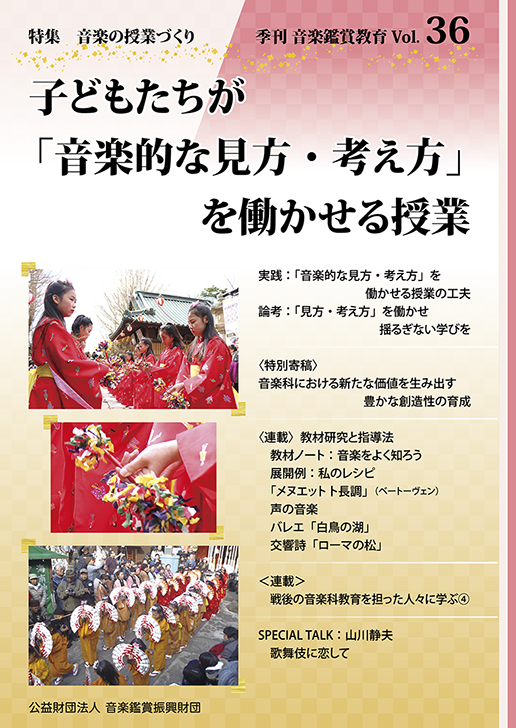
| 巻頭言 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 鑑賞授業の質を高めるには | 丸山忠璋 (元武蔵野音楽大学教授) | |||
| SPECIAL TALK | ||||
| 歌舞伎に恋して | ゲスト:山川静夫 (エッセイスト) | |||
| 特集:子どもたちが「音楽的な見方・考え方」を働かせる授業 | ||||
| テーマ設定の趣旨 | 「音楽的な見方・考え方」という概念が人生において生きて働くことに期待 | 加藤徹也 (武蔵野音楽大学教授・季刊「音楽鑑賞教育」編集委員) |
||
| 実践 | 「音楽的な見方・考え方」を働かせる授業の工夫 | |||
| 小学校 | 「音楽的な見方・考え方」が働く授業をめざして | 小室有香 (東京都小平市立小平第七小学校主任教諭) | ||
| 音楽の可視化から生まれる対話的な学び | 桶田加代 (千葉県千葉市立柏台小学校教諭) | |||
| 中学校 | 実感を伴った学びを作る「音楽的な見方・考え方」を働かせた授業を目指して | 佐塚繭子 (横浜国立大学教育学部附属横浜中学校教諭) | ||
| 音や音楽との出合いから始まる「音楽的な見方・考え方」を働かせた授業 | 小林美佳 (山梨大学教育学部附属中学校教諭) | |||
| 高等学校 | 「聴く力」「感じる力」「考えたり想像したりする力」「伝える力」 さまざまな資質・能力を総合的に働かせる鑑賞授業 |
河合紳和 (静岡県立清流館高等学校教諭) | ||
| 論考 | 「見方・考え方」を働かせ揺るぎない学びを | 小熊利明 (埼玉県立総合教育センター副所長) | ||
| まとめ | 生活場面も視野に入れて往還的な学習を位置付ける | 山下薫子 (東京藝術大学教授・季刊「音楽鑑賞教育」編集委員) |
||
| 教材研究と指導法 | ||||
| メヌエット ト長調(ベートーヴェン) | 教材ノート | 福中冬子 (東京藝術大学教授) | ||
| 展開例 | 高倉弘光 (筑波大学附属小学校教諭) | |||
| 声の音楽 | 教材ノート | 高松晃子 (聖徳大学教授) | ||
| 展開例 | 江田 司 (名古屋学院大学准教授) | |||
| バレエ《白鳥の湖》(チャイコフスキー) | 教材ノート | 奥田佳道 (音楽評論家) | ||
| 展開例 | 和田 崇 (東京音楽大学准教授) | |||
| 交響詩《ローマの松》(レスピーギ) | 教材ノート | 福井昭史 (長崎大学名誉教授) | ||
| 展開例 | 萬 司 (拓殖大学北海道短期大学教授) | |||
| 特別寄稿 | ||||
| 音楽科における新たな価値を生み出す豊かな創造性の育成 | 志民一成 (国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官/文化庁参事官(芸術文化担当)付教科調査官/文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官) |
|||
| 〈連載〉戦後の音楽科教育を担った人々に学ぶ〈最終回〉 | ||||
| 木村信之:音楽教育を理論面と実践面から研究 | 西園芳信 (鳴門教育大学名誉教授) | |||
| 本の紹介 | ||||
|
佐野 靖 (東京藝術大学教授) | |||
| 市販DISCを教材に | ||||
| 全日音研のページ | ||||
| 平成30年度全国大会〈部会大会〉へのご参加ありがとうございました | 小松康裕 (全日本音楽教育研究会本部事務局長) | |||
Vol.35(2018年10月発行)
B5判 64ページ
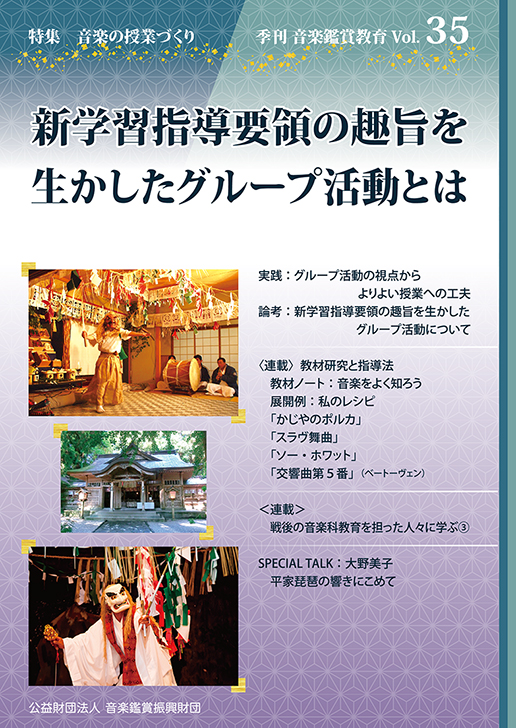
| 巻頭言 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 鑑賞の時間の確保について | 丸山忠璋 (元武蔵野音楽大学教授) | |||
| SPECIAL TALK | ||||
| 平家琵琶の響きにこめて ―鎮魂と祈りの語り― | ゲスト:大野美子 (平家琵琶 前田流平家詞曲相伝者) |
|||
| 特集:新学習指導要領の趣旨を生かしたグループ活動とは | ||||
| テーマ設定の趣旨 | グループ活動はなぜ必要なのか | 川池 聰 (季刊「音楽鑑賞教育」編集委員) | ||
| 実践 | グループ活動の視点からよりよい授業への工夫 | |||
| 小学校 | 音楽によるコミュニケーションを図れる児童を育成する | 山城怜菜 (東京都大田区立赤松小学校教諭) | ||
| 聴き合い、伝え合いながら、学び合う授業をめざして | 鈴木令子 (千葉県松戸市立幸谷小学校教諭) | |||
| 中学校 | 友だちと共有・共感の過程を大切にした鑑賞の授業 | 仲地綾子 (沖縄県うるま市立具志川中学校教諭) | ||
| 「主体的・対話的で深い学び」の視点に立ったグループ活動 | 松本 琢 (群馬県桐生市立広沢中学校教諭) | |||
| 高等学校 | アンサンブルを効果的に学ぶには ~ジグソー法を用いたグループ学習 | 猿賀智美 (青森県立弘前中央高等学校教諭) | ||
| 論考 | 新学習指導要領の趣旨を生かしたグループ活動について | 吉川武彦 (福島県飯館村立草野・飯樋・臼石小学校長) | ||
| まとめ | 授業改善につながるグループ活動を | 佐野享子 (季刊「音楽鑑賞教育」編集委員) | ||
| 教材研究と指導法 | ||||
| かじやのポルカ(ヨゼフ・シュトラウス) | 教材ノート | 福井昭史 (長崎大学名誉教授) | ||
| 展開例 | 高倉弘光 (筑波大学附属小学校教諭) | |||
| スラヴ舞曲(ドヴォルザーク) | 教材ノート | 奥田佳道 (音楽評論家) | ||
| 展開例 | 江田 司 (名古屋学院大学准教授) | |||
| ソー・ホワット(マイルス・デイヴィス) | 教材ノート | 菊地成孔 (ジャズ・ミュージシャン) | ||
| 展開例 | 和田 崇 (東京音楽大学准教授) | |||
| 交響曲第5番 ハ短調(ベートーヴェン) | 教材ノート | 福中冬子 (東京藝術大学教授) | ||
| 展開例 | 萬 司 (拓殖大学北海道短期大学教授) | |||
| 〈連載〉戦後の音楽科教育を担った人々に学ぶ | ||||
| 真篠 将:音楽科教育の素地固めに尽力した先達の名著に学ぶ | 木村博文 (元日本教育音楽協会会長) | |||
| 本の紹介 | ||||
|
佐野 靖 (東京藝術大学教授) | |||
| 市販DISCを教材に | ||||
| 全日音研のページ | ||||
| 平成30年度の全日音研各支部長の皆様をご紹介します | 小松康裕 (全日本音楽教育研究会本部事務局長) | |||
| 音鑑の事業紹介 | ||||
|
||||
Vol.34(2018年7月発行)
B5判 64ページ
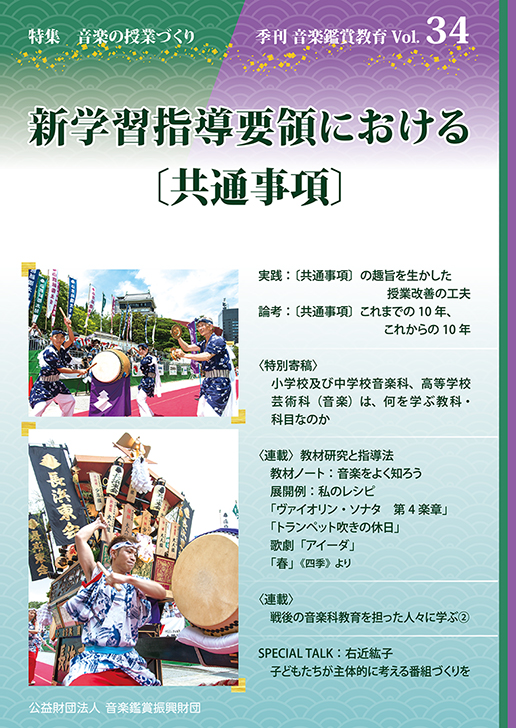
| 巻頭言 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 音楽は何処にあるか? | 丸山忠璋 (元武蔵野音楽大学教授) | |||
| SPECIAL TALK | ||||
| 子どもたちが主体的に考える番組づくりを | ゲスト:右近紘子 (NHK for School 音楽番組ディレクター) |
|||
| 特集:新学習指導要領における〔共通事項〕 | ||||
| テーマ設定の趣旨 | 〔共通事項〕の新しい位置付けとその指導 | 藤沢章彦 (東京女子体育大学講師・季刊「音楽鑑賞教育」編集委員) |
||
| 実践 | 〔共通事項〕の趣旨を生かした授業改善の工夫 | |||
| 小学校 | 「教師と子供の中間で〔共通事項〕が結節する」鑑賞授業を | 高倉弘光 (筑波大学附属小学校教諭) | ||
| 生きて働く知識の習得を図る「題材を貫く課題」 | 門田集二 (山口大学教育学部附属光小学校主幹教諭) | |||
| ICTを活用し、〔共通事項〕を支えに音楽的な見方・考え方を働かせて実現する、新しい鑑賞授業の創造 | 小梨貴弘 (埼玉県戸田市立戸田東小学校教諭) | |||
| 中学校 | 音楽を丸ごと味わうための〔共通事項〕 | 安部文江 (長野県御代田町立御代田中学校教諭) | ||
| 〔共通事項〕の趣旨をふまえ、「音楽的な見方・考え方」を働かせた授業とは | 佐藤太一 (埼玉大学教育学部附属中学校校内教頭) | |||
| 論考 | 〔共通事項〕これまでの10年、これからの10年 | 藤井浩基 (島根大学教授) | ||
| まとめ | 「音楽的な見方・考え方」を働かせて「知覚したことと感受したことの関わりを考える」 | 加藤富美子 (東京音楽大学教授・季刊「音楽鑑賞教育」編集委員) |
||
| 教材研究と指導法 | ||||
| ヴァイオリン・ソナタ イ長調 第4楽章(フランク) | 教材ノート | 奥田佳道 (音楽評論家) | ||
| 展開例 | 高倉弘光 (筑波大学附属小学校教諭) | |||
| トランペット吹きの休日(アンダソン) | 教材ノート | 福中冬子 (東京藝術大学教授) | ||
| 展開例 | 江田 司 (名古屋学院大学准教授) | |||
| 歌劇《アイーダ》(ヴェルディ) | 教材ノート | 福中冬子 (東京藝術大学教授) | ||
| 展開例 | 和田 崇 (東京音楽大学講師) | |||
| 春(《四季》より)(ヴィヴァルディ) | 教材ノート | 福井昭史 (長崎大学名誉教授) | ||
| 展開例 | 萬 司 (拓殖大学北海道短期大学教授) | |||
| 特別寄稿 | ||||
| 小学校及び中学校音楽科、高等学校芸術科(音楽)は、何を学ぶ教科・科目なのか | 臼井 学 (国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官・(併任)文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官) |
|||
| 〈連載〉戦後の音楽科教育を担った人々に学ぶ | ||||
| 大和淳二:「音楽科で何を身に付けるのか」の道筋を示す | 川池聰 (公益財団法人音楽鑑賞振興財団理事) | |||
| 本の紹介 | ||||
|
佐野 靖 (東京藝術大学教授) | |||
| 市販DISCを教材に | ||||
| 全日音研のページ | ||||
| 平成最後の全国大会〈部会大会〉! 校種を越えてご参加下さい | 小松康裕 (全日本音楽教育研究会本部事務局長) | |||
Vol.33(2018年4月発行)
B5判 72ページ
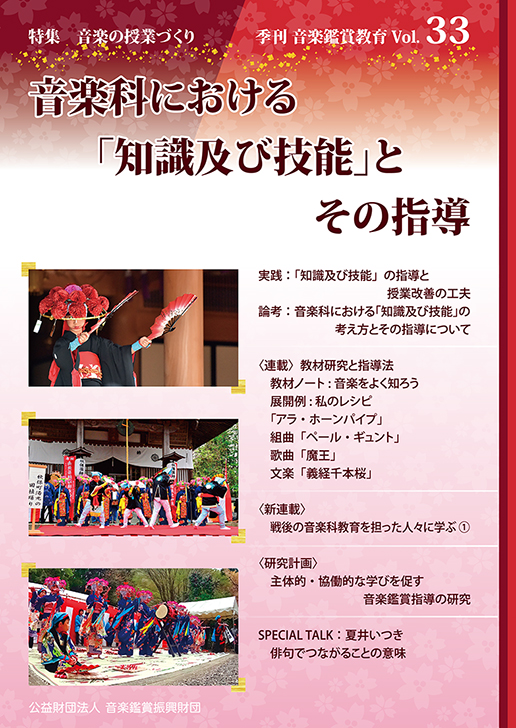
| 巻頭言 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 耳朶の奥底に眠る | 丸山忠璋 (元武蔵野音楽大学教授) | |||
| SPECIAL TALK | ||||
| 俳句でつながることの意味 ――俳句のある人生を楽しむ―― |
ゲスト:夏井いつき (俳人) | |||
| 特集:音楽科における「知識及び技能」とその指導 | ||||
| テーマ設定の趣旨 | 学習活動のなかに、その定着や変容の連続性を読み取る | 山下薫子 (東京藝術大学教授・季刊「音楽鑑賞教育」編集委員) |
||
| 実践 | 「知識及び技能」の指導と授業改善の工夫 | |||
| 小学校 | 「知識」の習得につながる音楽会の取り組み ~音楽物語「くるみ割り人形」の実践を通して~ |
西沢久美 (兵庫県神戸市立神戸祇園小学校主幹教諭) | ||
| 鑑賞指導における音楽科の「知識」とは何か | 河崎秋彦 (茨城県取手市立取手小学校教諭) | |||
| 学びの質が高まる授業づくり | 蝦真理子 (埼玉県日高市立高麗川小学校教諭) | |||
| 中学校 | 生きて働く「知識及び技能」の育成を目指して | 勝山幸子 (東京都港区立六本木中学校主任教諭) | ||
| よりよい授業づくりをめざして | 田平英嗣 (島根県松江市立島根中学校教諭) | |||
| 論考 | 音楽科における「知識及び技能」の考え方とその指導について | 副島和久 (佐賀県教育センター研究課長) | ||
| まとめ | 知識及び技能の習得と活用の過程の探求を通して | 加藤徹也 (武蔵野音楽大学教授・季刊「音楽鑑賞教育」編集委員) |
||
| 教材研究と指導法 | ||||
| アラ・ホーンパイプ | 教材ノート | 福中冬子 (東京藝術大学教授) | ||
| 展開例 | 高倉弘光 (筑波大学附属小学校教諭) | |||
| 組曲《ペール・ギュント》(「朝」) | 教材ノート | 奥田佳道 (音楽評論家) | ||
| 展開例 | 江田 司 (名古屋学院大学准教授) | |||
| 歌曲「魔王」 | 教材ノート | 福井昭史 (長崎大学名誉教授) | ||
| 展開例 | 萬 司 (拓殖大学北海道短期大学教授) | |||
| 文楽《義経千本桜》 二段目「渡海屋・大物浦の段」 | 教材ノート | 垣内幸夫 (京都教育大学名誉教授) | ||
| 展開例 | 和田 崇 (東京音楽大学講師) | |||
| 〈新連載〉戦後の音楽科教育を担った人々に学ぶ | ||||
| 浜野政雄:音楽科教育における人間と音楽の関わりを追究 | 山本文茂 (東京藝術大学名誉教授) | |||
| 本の紹介 | ||||
|
佐野 靖 (東京藝術大学教授) | |||
| 市販DISCを教材に | ||||
| 全日音研のページ | ||||
| のびる・ひろがる・ひびきあう ~実りある音楽の授業~ 〈平成30年度全日本音楽教育研究会全国大会和歌山大会のご案内〉 |
岩本浩志 (大会事務局長) | |||
| 平成29年度 第50回 音楽鑑賞教育振興 論文・作文募集 研究助成の部 入選研究計画論文 | ||||
| 主体的・協働的な学びを促す音楽鑑賞指導の研究 ――教材研究の新たな視点に基づく授業構想を通して―― |
音楽鑑賞教育実践研究会 (代表:山本幸正 (国立音楽大学)) |
|||
| 音鑑の事業紹介 | ||||
|
||||