出版・販売季刊「音楽鑑賞教育」: 2019年度バックナンバー
Vol.40(2020年1月発行)
B5判 64ページ
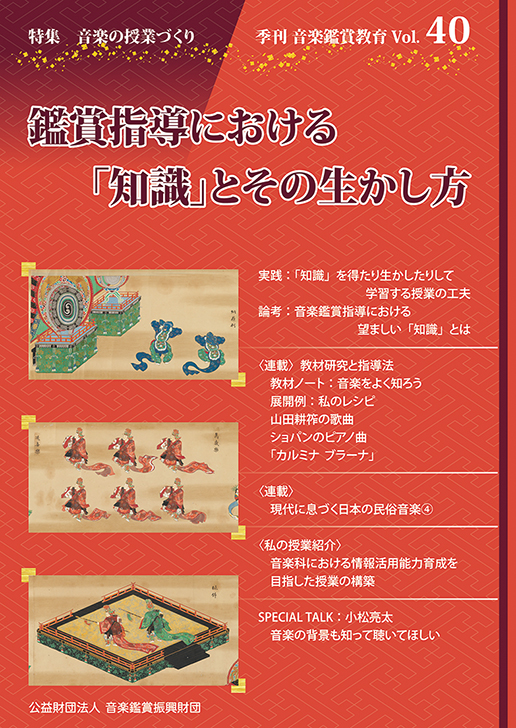
| 巻頭言 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 理解を伴った音楽享受を | 山本文茂 (東京藝術大学名誉教授) | |||
| SPECIAL TALK | ||||
| 音楽の背景も知って聴いてほしい | ゲスト:小松亮太 (バンドネオン奏者) | |||
| 特集:鑑賞指導における「知識」とその生かし方 | ||||
| テーマ設定の趣旨 | 「ソナタ形式」を例として | 山下薫子 (東京藝術大学教授・季刊「音楽鑑賞教育」編集委員) |
||
| 実践 | 「知識」を得たり生かしたりして学習する授業の工夫 | |||
| 小学校 | 「音・音楽を聴く」見方・考え方を働かせて、子どもと一緒に「知識」を見つけ習得する授業 | 山上美香 (香川県高松市立花園小学校教諭) | ||
| 実感を伴った、生きて働く鑑賞教育 | 袴田文子 (静岡県浜松市立船越小学校教諭) | |||
| 中学校 | 鑑賞の学習で得た「知識」を生かして | 森岡美奈子 (東京都世田谷区立深沢中学校主幹教諭) | ||
| 高等学校 | 知的好奇心を刺激し知識を活用する授業展開 | 鈴木美奈子 (早稲田大学系属早稲田実業学校中等部・高等部教諭) |
||
| 過去と今をつなぐ授業 | 上原由美 (埼玉県立羽生第一高等学校教諭) | |||
| 論考 | 音楽鑑賞指導における望ましい「知識」とは | 後藤 丹 (作曲家・上越教育大学名誉教授) | ||
| まとめ | 鑑賞する喜びにつながっていく「知識」とその生かし方 | 加藤富美子 (東京音楽大学客員教授・季刊「音楽鑑賞教育」編集委員) |
||
| 教材研究と指導法 | ||||
| 山田耕筰の歌曲 | 教材ノート | 山田啓明 (鳴門教育大学准教授) | ||
| 展開例 | 高倉弘光 (筑波大学附属小学校教諭) | |||
| ショパンのピアノ曲 | 教材ノート | 福中冬子 (東京藝術大学教授) | ||
| 展開例 | 長者久保希史子 (青森県八戸市立北稜中学校教頭) | |||
| カルミナ ブラーナ | 教材ノート | 奥田佳道 (音楽評論家) | ||
| 展開例 | 小野瀬照夫 (埼玉県立伊奈学園総合高等学校教諭) | |||
| 特別寄稿 | ||||
| 音楽科における他者と協働する学びの意義と課題 | 志民一成 (国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官/文化庁参事官(芸術文化担当)付教科調査官/文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官) |
|||
| 〈連載〉現代に息づく日本の民俗音楽 | ||||
| 口伝デンデン ~オノマトペ? | 小岩秀太郎 (公益社団法人全日本郷土芸能協会事務局次長・理事) |
|||
| 本の紹介 | ||||
|
佐野 靖 (東京藝術大学教授) | |||
| 市販DISCを教材に | ||||
| 私が工夫している授業紹介 | ||||
| 音楽科における情報活用能力育成を目指した授業の構築 | 齊藤貴文 (北海道教育大学附属釧路中学校教諭) | |||
| 全日音研のページ | ||||
| 令和元年度全日音研全国大会東京大会〈総合大会〉 ~全日音研発足50周年記念~ 多くの皆様のご参加ありがとうございました | 小松康裕 (全日本音楽教育研究会本部事務局長) | |||
| 音鑑の事業紹介 | ||||
| 音鑑・ICT勉強会2019 | ||||
Vol.39(2019年10月発行)
B5判 64ページ
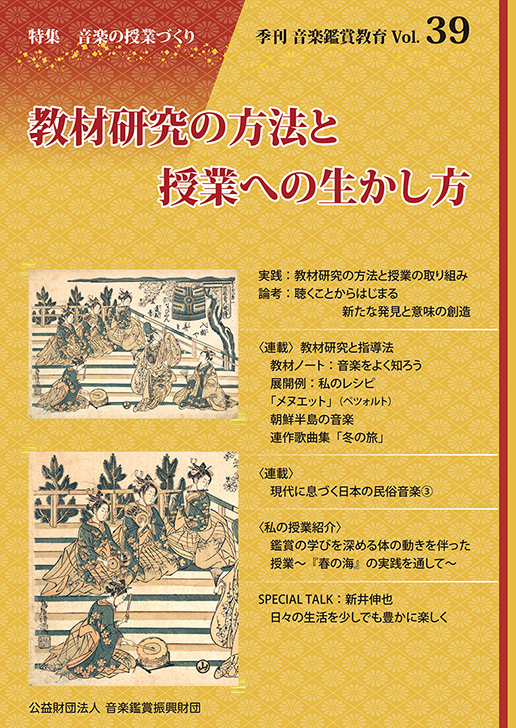
| 巻頭言 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 教材の価値を多面的に探る | 山本文茂 (東京藝術大学名誉教授) | |||
| SPECIAL TALK | ||||
| 日々の生活を少しでも豊かに楽しく | ゲスト:新井伸也 (すみだトリフォニーホール音楽事業主任) |
|||
| 特集:教材研究の方法と授業への生かし方 | ||||
| テーマ設定の趣旨 | なぜ教材研究が必要なのか ~教材研究の考え方と進め方~ | 川池 聰 (季刊「音楽鑑賞教育」編集委員) | ||
| 実践 | 教材研究の方法と授業の取り組み | |||
| 小学校 | 子どもたちの学びを深める教材研究について | 沖津陽子 (徳島県阿波市立市場小学校教諭) | ||
| 「ハンガリー舞曲第5番」で音楽のエネルギーを感じ取る | 守田映実 (東京都中野区立南台小学校主任教諭) | |||
| 中学校 | 音楽を愛好する心情を育む鑑賞の授業を目指して | 関ちえみ (北海道旭川市立東明中学校教諭) | ||
| 「音楽って面白い!」と思わせる授業を目指して | 松浦昌江 (奈良県広陵町立真美ヶ丘中学校教諭) | |||
| 高等学校 | 心豊かな生活を創造するために | 保坂悠紀 (東京都立足立西高等学校教諭) | ||
| 論考 | 聴くことからはじまる新たな発見と意味の創造 | 北山敦康 (静岡大学名誉教授) | ||
| まとめ | 教材研究の視点と方法を再確認する | 加藤徹也 (武蔵野音楽大学教授・季刊「音楽鑑賞教育」編集委員) |
||
| 教材研究と指導法 | ||||
| メヌエット(ペツォルト) | 教材ノート | 福井昭史 (長崎大学名誉教授) | ||
| 展開例 | 江田 司 (名古屋学院大学准教授) | |||
| 朝鮮半島の音楽 | 教材ノート | 植村幸生 (東京藝術大学教授) | ||
| 展開例 | 和田 崇 (東京音楽大学教授) | |||
| 連作歌曲集《冬の旅》 | 教材ノート | 奥田佳道 (音楽評論家) | ||
| 展開例 | 原 大介 (お茶の水女子大学附属高等学校教諭) | |||
| 〈連載〉現代に息づく日本の民俗音楽 | ||||
| カネの魔力 | 小岩秀太郎 (公益社団法人全日本郷土芸能協会事務局次長・理事) |
|||
| 本の紹介 | ||||
|
佐野 靖 (東京藝術大学教授) | |||
| 市販DISCを教材に | ||||
| 私が工夫している授業紹介 | ||||
| 鑑賞の学びを深める体の動きを伴った授業 ―「春の海」の実践を通して― | 仙波仁子 (千葉県佐倉市立上志津小学校教諭) | |||
| 全日音研のページ | ||||
|
小松康裕 (全日本音楽教育研究会本部事務局長) | |||
| 音鑑の事業紹介 | ||||
| 音鑑・夏の勉強会2019「よりよい授業を求めて」 | ||||
Vol.38(2019年7月発行)
B5判 64ページ
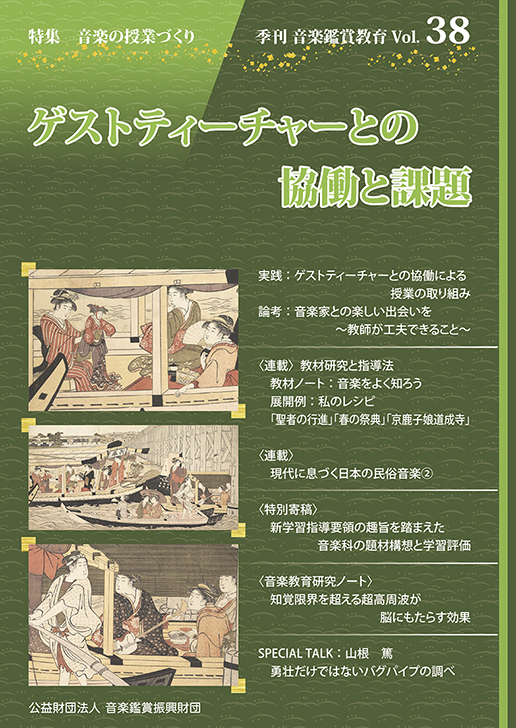
| 巻頭言 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 母校の訪問指導を中心に | 山本文茂 (東京藝術大学名誉教授) | |||
| SPECIAL TALK | ||||
| 勇壮だけではないバグパイプの調べ | ゲスト:山根 篤 (東京パイプバンド代表) | |||
| 特集:ゲストティーチャーとの協働と課題 | ||||
| テーマ設定の趣旨 | 子どもたちに豊かな音楽経験を | 佐野享子 (横浜高等教育専門学校講師・季刊「音楽鑑賞教育」編集委員) |
||
| 実践 | ゲストティーチャーとの協働による授業の取り組み | |||
| 小学校 | ゲストティーチャーとつくる「ミュージック・デリバリー」 | 新井 正 (千葉県浦安市立東小学校教諭) | ||
| ゲストティーチャーとの協働による民俗芸能への取り組み 〜二本松市秋葉神社祭礼のお囃子の実践から〜 | 山崎純子 (福島県二本松市立原瀬小学校教諭) | |||
| 中学校 | ゲストティーチャーの音から感動を | 沼田幸子 (石川県金沢市立長田中学校教諭) | ||
| 高等学校 | 音そのものの質感や、音や音楽の美しさを直接的に感じ取る | 矢野一誠 (香川県立飯山高等学校教諭) | ||
| ゲストティーチャー | それぞれの立場で議論を重ねて | 深海さとみ (箏曲演奏家(宮城社大師範・深海邦楽会主宰)) | ||
| 論考 | 音楽家との楽しい出会いを 〜教師が工夫できること〜 | 林 睦 (滋賀大学教授) | ||
| まとめ | 教員の準備と努力の上に | 藤沢章彦 (東京女子体育大学講師・季刊「音楽鑑賞教育」編集委員) |
||
| 教材研究と指導法 | ||||
| 聖者の行進 | 教材ノート | 吉成 順 (国立音楽大学教授) | ||
| 展開例 | 高倉弘光 (筑波大学附属小学校教諭) | |||
| バレエ音楽《春の祭典》(ストラヴィンスキー) | 教材ノート | 福中冬子 (東京藝術大学教授) | ||
| 展開例 | 長者久保希史子 (青森県八戸市立北稜中学校教頭) | |||
| 歌舞伎《京鹿子娘道成寺》(初世杵屋弥三郎) | 教材ノート | 福井昭史 (長崎大学名誉教授) | ||
| 展開例 | 小峰和則 (東京都立新宿高等学校主幹教諭) | |||
| 特別寄稿 | ||||
| 新学習指導要領の趣旨を踏まえた音楽科の題材構想と学習評価 | 臼井 学 (国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官/(併任)文化庁参事官(芸術文化担当)付教科調査官/(併任)文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官) |
|||
| 〈連載〉現代に息づく日本の民俗音楽 | ||||
| 「ササラ」が“ささらほうさら”すぎる件 | 小岩秀太郎 (公益社団法人全日本郷土芸能協会事務局次長・理事) |
|||
| 特別寄稿 音楽教育研究ノート | ||||
| 知覚限界を超える超高周波が脳にもたらす効果 ―ハイパーソニック・エフェクト | 仁科エミ (放送大学教授) | |||
| 本の紹介 | ||||
|
佐野 靖 (東京藝術大学教授) | |||
| 市販DISCを教材に | ||||
| 全日音研のページ | ||||
| 令和時代幕開けの全国大会 東京大会〈総合大会〉〜全日音研50周年記念〜 第2次案内[参加申し込み]ホームページに掲載しました | 小松康裕 (全日本音楽教育研究会本部事務局長) | |||
Vol.37(2019年4月発行)
B5判 68ページ
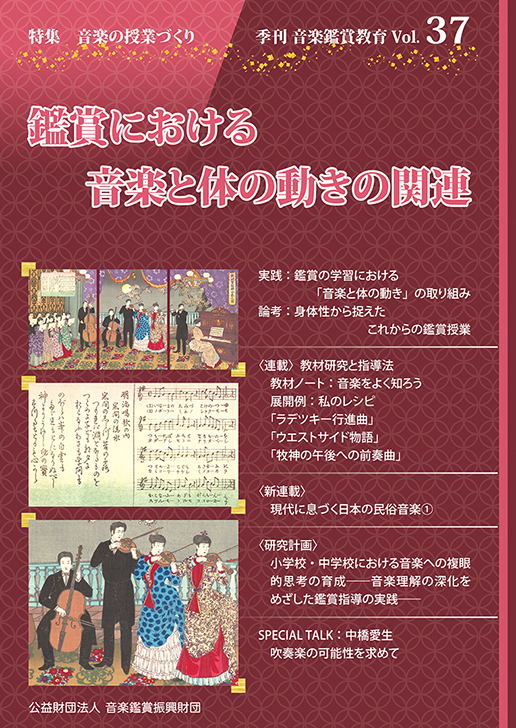
| 巻頭言 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 音楽と言葉と体の動き | 山本文茂 (東京藝術大学名誉教授) | |||
| SPECIAL TALK | ||||
| 吹奏楽の可能性を求めて ―合奏する喜び、音楽を創る喜び― | ゲスト:中橋愛生 (作曲家・東京音楽大学准教授) | |||
| 特集:鑑賞における音楽と体の動きの関連 | ||||
| テーマ設定の趣旨 | 感性の根源に「体の動き」の働きをみる | 山下薫子 (東京藝術大学教授・季刊「音楽鑑賞教育」編集委員) |
||
| 実践 | 鑑賞の学習における「音楽と体の動き」の取り組み | |||
| 小学校 | 鑑賞と表現を行き来する | 湯澤 卓 (上越教育大学附属小学校教諭) | ||
| 郷土の音楽を体感し、良さを最大限感じる | 金子 緑 (東京都日の出町立大久野小学校教諭) | |||
| 中学校 | 鑑賞の学習における「音楽と体の動き」について | 片岡憂佳 (千葉県野田市立東部中学校教諭) | ||
| 鑑賞授業における効果的な「体を動かす活動」 | 石原孝一 (山梨県甲斐市立玉幡中学校教諭) | |||
| 高等学校 | 音楽と一体化し生徒の感覚を大切にした鑑賞にするために ~「旋律ライブドローイング」「エア鼓体験」を取り入れた実践 | 広戸茉里 (島根県立安来高等学校教諭) | ||
| 論考 | 身体性から捉えたこれからの鑑賞授業 | 伊野義博 (新潟大学教授) | ||
| まとめ | 鑑賞活動における「身体を通した学び」の指針 | 加藤富美子 (東京音楽大学客員教授・季刊「音楽鑑賞教育」編集委員) |
||
| 教材研究と指導法 | ||||
| ラデツキー行進曲(ヨハン・シュトラウス1世) | 教材ノート | 奥田佳道 (音楽評論家) | ||
| 展開例 | 江田 司 (名古屋学院大学准教授) | |||
| ウエストサイド物語(バーンスタイン) | 教材ノート | 福中冬子 (東京藝術大学教授) | ||
| 展開例 | 和田 崇 (東京音楽大学准教授) | |||
| 牧神の午後への前奏曲(ドビュッシー) | 教材ノート | 福井昭史 (長崎大学名誉教授) | ||
| 展開例 | 小峰和則 (東京都立新宿高等学校主幹教諭) | |||
| 〈新連載〉現代に息づく日本の民俗音楽 | ||||
| 変化する郷土芸能 | 小岩秀太郎 (公益社団法人全日本郷土芸能協会事務局次長・理事) |
|||
| 本の紹介 | ||||
|
佐野 靖 (東京藝術大学教授) | |||
| 市販DISCを教材に | ||||
| 全日音研のページ | ||||
| 2019年全日本音楽教育研究会全国大会 東京大会(総合大会) 大会開催に伴う関連行事のお知らせ | 小松康裕 (全日本音楽教育研究会本部事務局長) | |||
| 平成30年度 第51回 音楽鑑賞教育振興 論文・作文募集 研究助成の部 入選研究計画論文 | ||||
| 小学校・中学校における音楽への複眼的思考の育成 ―音楽理解の深化をめざした鑑賞指導の実践― |
北海道教育大学札幌校音楽科教育研究グループ (代表:寺田貴雄 (北海道教育大学札幌校)) |
|||
| 音鑑の事業紹介 | ||||
|
||||